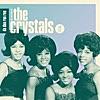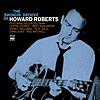スペクターに心酔していたジーン・ピットニーが
「Uptown」に影響されて書いた「He's A Rebel」
1962年5月、ロネッツを連れて、ロサンゼルスに戻ったフィル・スペクターはゴールド・スター・スタジオに駆け込んで、彼女たちのデモ録音を行った。だが、スペクターはもっと大きな果たすべき課題を抱えていた。それはニューヨークでジーン・ピットニーから聴かされた「He’s A Rebel」という曲をクリスタルズの新曲として、一刻も早くレコーディングすることだった。
ジーン・ピットニーは1960年に自作曲の「(I Wanna) Love My Life Away」でデビューしたシンガーだった。1961年の「Louisiana Mama」は米本国ではヒットしなかったが、日本では飯田久彦が歌った漣健児による訳詞バージョンの大ヒットで、よく知られている。さらに同年、ピットニーはキャロル・キング&ジェリー・ゴフィンの「Every Breath I Take」をヒットさせるが、このレコーディング・セッションには、フィル・スペクターが協力した。ピットニーを売り出したミュージコー・レコードは、エルヴィス・プレスリーに数多くの曲を書いたソングライターのアーロン・シュローダーが興したレーベルで、シュローダーはスペクターのことも高く買っていたのだ。


Gene Pitney - Every Breath I Take (1961, Vinyl) | Discogs
セッションを通じて、ピットニーも1歳年上のスペクターの才能に心酔するようになった。そして、バリー・マン&シンシア・ウェルズが書いたクリスタルズの「Uptown」に影響され、「Uptown」に続く彼女たちのシングルを想定して、「He’s A Rebel」を書き上げた。シュローダーの事務所で、ピットニーが作った曲を聴いたスペクターは、これは絶対にヒットすると確信した。彼がリバティを辞めた最大の理由は、その「He’s A Rebel」をリバティに渡さず、フィレスでレコーディングしたくなったからだった。
しかし、ロサンゼルスのスペクターのもとにシュローダーから送られてくるはずの「He’s A Rebel」のデモは、6月の終わりにならないと届かなかった。その間に、シュローダーは実は二股をかけていた。スペクターが気に入った「He’s A Rebel」をリバティのスナッフ・ギャレットにも聴かせたのだ。そして、ギャレットもスペクター同様、ピットニーのその曲をヒット間違い無しと踏んでいた。

ゴールド・スターでのクリスタルズの新曲録音は7月13日にセッティングされた。アレンジャーのジャック・ニッチェとサックス奏者のスティーヴ・ダグラスがレコーディング・メンバーを集めることになった。彼らが招集したのは後にレッキング・クルーの中心を成す強者たちだった。ドラマーはハル・ブレイン、ピアニストはラリー・ネクテルとアル・デルロイ、ギタリストはハワード・ロバーツとトミー・テデスコ、ベーシストはレイ・ポールマンとジミー・リード。メンバーの大半にとって、この日がスペクターとの初顔合わせだったという。

クリスタルズ「He's A Rebel」のリード・シンガーは
ブロッサムズのダーレン・ラヴ
この日のセッションはミュージシャンをブッキングするだけでは始まらなかった。というのも、主役となるはずのクリスタルズはロサンゼルスには居なかったからだ。彼女たちは飛行機が嫌いで、LA行きを拒否したせいだったというエピソードが語られることが多いが、それはスペクターが周囲にそう説明してきたからだろう。
キングスレイ・アボットが編纂した『音の壁の向こう側 フィル・スペクター読本』(Little Symphonies:A Phil Spector Reader)には1980年に『Goldmine』誌に掲載されたクリスタルズのメンバー、ディー・ディー・ケニブリューへのインタビューが含まれている。それを読むと、クリスタルズはジーン・ピットニーが自分たちのために書いた「He’s A Rebel」をリハーサルしていた。だが、彼女たちの歌うスタイルをスペクターは気に入らなかった。それ故、スペクターは最初からその曲の録音に本物のクリスタルズを使うつもりがなかったようだ。クリスタルズの3人はロサンゼルスでレコーディングが行われているとはつゆ知らず、高校に通っていた。
代わりのガールズ・グループを見つけるのはレスター・シルの仕事になった。シルが推薦したのは、ロサンゼルスでリズム&ブルースのバックグラウンド・コーラスに活躍していたブロッサムズだった。彼女たちは1950年代前半からR&Bグループのリチャード・ベリー&ドリーマーズのドリーマーズとして活動。ブロッサムズに改名後の1956年に、リード・ボーカルがダーレン・ラヴに交替した。サム・クックやボビー・ダーリンのヒット曲でも歌っているブロッサムズは名うてのプロフェッショナルで、最年少のラヴももはやティーンエイジャーではなかった。

「He’s A Rebel」を歌うことになったダーレン・ラヴも過去にスペクターと仕事したことはなかったし、クリスタルズというグループも知らなかったという。デイヴ・トンプソン著の『Phil Spector: Wall of Pain』には、ラヴのこんな回想が綴られてている。セッションでラヴの歌唱は盛り上がり過ぎ、エンディング・パートではリズムがズレてしまっていた。音符がしばしば16分の裏に入ってしまう部分だろう。彼女はもう一度、やり直させて、とスペクターに頼んだが、スペクターはそのミスが気に入ったと言って、OKを出した。
続いて、ブロッサムズの残りのメンバーも呼ばれ、男性シンガーのボビー・シーンとともにバック・コーラスを録音した。スペクターが彼女たちに支払ったギャラは3,000ドルだったという。当時としては法外なその金額故に、エキサイティングな経験になったが、ラヴにとってはそれはセッション・シンガーとしての仕事の一つに過ぎず、その曲をもう一度、耳にすることは無いと思っていたという。
ダブル・バンドが奏でたウォール・オブ・サウンド
Broad Monoでのステレオ全盛への“反逆”
フィル・スペクターが“ウォール・オブ・サウンド”を築き上げるのに必要とした最大のパートナーであるエンジニアのラリー・レヴィンも、この日がスペクターとの初仕事だった。スペクターの信頼するスタン・ロスはハワイに出張中だったのだ。
1928年生まれのラリー・レヴィンはロスの1歳年上の従兄弟で、1958年のテディ・ベアーズのセッションのころにもゴールド・スターで働いていた。だが、スペクターのことは癇に障るガキとみなしていて、接触を避けていたようだ。ゴールド・スターのAスタジオに呼ばれたミュージシャンが集まると、レヴィンはあっけに取られた。ベース奏者まで2人居るというのは、どう考えてもオーバー・ブッキングだったからだ。

http://www.larrylevinerecordingengineer.com/
スペクターにとっても、この日のセッションのどこまでが計画的だったのかは分からない。あるいは、ニッチェとダグラスがミュージシャンに声をかけ過ぎて、ベーシストは本当にオーバー・ブッキングされてしまったのかもしれない。さまざまな偶然も重なりあって、この日のセッションが“ウォール・オブ・サウンド”のバースデイになったのは間違い無いだろう。
「He’s A Rebel」のアレンジはシンプルなものだった。ジーン・ピットニーによれば、彼が作ったデモと変わりないという。スペクターはレコーディングを急いでいたため、ジャック・ニッチェにオーケストレーションに書かせる余裕が無かったのかもしれない。
“ウォール・オブ・サウンド”というと、エコーの塊のようなイメージを抱きがちだが、「He’s A Rebel」ではゴールド・スターのエコー・チェンバーはほとんど使われていない。だが、この曲はそれまでのスペクター・サウンドとは違う次元に到達していた。それはスタジオAにミュージシャンを詰め込み、複数のプレイヤーに同じ楽器を演奏させ、カブリの多いマルチマイク・レコーディングを行うことから生まれた。“音の壁”の構築はそこから始まったことを「He’s A Rebel」は物語っている。

The Crystals - He's A Rebel (1962, Vinyl) | Discogs
スペクターにとっては、それはハイスクール時代にマイケル・シュリーヴと語り合っていたアイディアの具現でもあった。2人は“Broad Mono”(幅のあるモノ)という言葉を使っていたという。ダブリングやフェイジングを効果的に使うことによって、モノラルであっても、幅を感じさせるサウンドを作り出す。逆から言えば、音を点にしないことをスペクターは追求してきた。その方向性は当時から全くぶれていなかった。
「He’s A Rebel」(彼は反逆者)という曲で、スペクター・サウンドが次のレベルに進んだことは象徴的でもある。それはまさしく、当時のレコード業界の趨勢に対する反逆だったからだ。スペクターのミュージシャンとしてのキャリアはステレオ時代の幕開けとともに始まった。アトランティック時代には彼は8trでのレコーディングも経験している。しかし、音の分離や解像度を良くする方向には目もくれず、すべてが一体となったカオスの中に美を見出すことに狂おしい情熱を傾けたのがフィル・スペクターだった。
レトロスペクティブな方法論を選び取ることは、今日のレコーディング現場においては珍しくない。だが、オーディオ・エンジニアリングが日進月歩だった1960年代において、スペクターのようにそれに背を向けた人間は他に見当たらない。その意味でも、彼は反逆者であり、先駆者だった。
「He's A Rebel」のサウンドを決定付けた
ゴールド・スター・スタジオの音響特性
初顔合わせだらけのスタジオで、スペクター以外の全員が半信半疑でセッションに臨んでいたのは想像に難くない。例によって、スペクターは時間を気にすることなく、彼の望むフィーリングが得られるまで、シンプルな3分間ほどの曲をミュージシャンたちに何度でも演奏させた。
ミュージシャンの間にはパーティションを置かないというのが、スペクターからレヴィンへのリクエストだった。それでもドラム・サウンドのほかの楽器へのリーケージが大きくならず、すべての楽器がうまく収録できるように、レヴィンは楽器の配置とマイキングを考えねばならなかった。とりわけ、アコースティック・ギターの収録がスペクターのセッションではいつも困難を抱えたとレヴィンは語っている。
当時のゴールド・スターのコントロール・ルームにはビル・パットナムのUNITED AUDIO(後のUNIVERSAL AUDIO/UREI)に特注した12chコンソールが置かれていた。レコーダーはAMPEX 300の3tr。1trにオケを、1trにダーレン・ラヴのリード・ボーカルを、1trにバック・コーラスをというシンプルなトラック・シートだったろう。それ故、ステレオ・ミックスは不可能だった。その後のクリスタルズのレコーディングでも、ステレオ版は作られたことがない。
頭の中で思い描いたサウンドを妥協なく求める一方で、スペクターは機材には全く無頓着だった。ゴールド・スターのコントロール・ルームに備えられていたアウトボードはPULTECのEQくらいで、リミッター/コンプレッサーはマスタリング・ルームにしか無かったようだ。スタジオのサウンド・カラーを決定付けていたのは機材ではなく、レコーディング・ブースの壁の鉛入りアクリル塗料の音響特性だったとレヴィンは分析している。
コントロール・ルームの壁面はほとんどがパーティクル・ボードで、モニターにはALTECの通称“銀箱”(612)がつるされていた。デイヴ・ゴールドが手作りしたコントロール・ルームは良い音がしたが、サウンドの色付けが強く、そこで作った音がほかの場所で聴いたときにどういう音になるかは判断しづらかったそうだ。加えて、スペクターは大音量でのモニターを好んだ。

コントロール・ルームの轟音に一体、何が起こっているのかとメンバーは顔を見合わせていたとスティーヴ・ダグラスは回想している。だが、ついにスペクターが望むバランスを見つけたOKテイクを聴いて、自分たちが何かこれまでにない新しいものを作り上げたことに気付いた。テイクに満足したスペクターはご機嫌で、ミュージシャンの中でもとりわけ、ハル・ブレインのドラムに強い感銘を受けていた。フィレスでのスペクターは、ミュージシャンへの金払いも良かったから、レッキング・クルーの面々とはすぐに良い関係が築かれていった。ただし、ギターのハワード・ロバーツだけは例外だった。

10代半ばのスペクターにジャズ・ギターを教えていたロバーツは、高価なスーツを着込んだプロデューサーがシャイな少年だったころを知っていた。だが、2人の間に親密さはもはや無かった。スペクターは今や絶対的なスタジオの独裁者だった。
スペクターのセッションはいつもギター・パートを固めるところからスタートした。その後、すべての楽器のアレンジがチェックされ、マイキング、ミキシングのバランスが完ぺきになるまで、ギタリストには単調なコードをひたすら弾き続ける苦行が求められた。“ウォール・オブ・サウンド”においては、ギターのコードはほとんど休符が無く、ギタリストはネックを握り続けなければならなかった。セッションの途中で、ロバーツはもう二度とスペクターとは仕事しないと心に決めていた。
一方、もう一人のギタリスト、トミー・テデスコはゴールド・スターでのセッションが終わると、次の仕事場であるユナイテッド・レコーディングに向かっていた。

高橋健太郎
音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。
Twitterアカウントは@kentarotakahash
Photo:Hiroki Obara