バーバンクでは生まれていないワーナーの“バーバンク・サウンド”
1960年代後半から1970年代の前半にかけて、QUAD EIGHT〜ELECTRODYNEのコンソールはアメリカのスタジオ・シーンでポピュラーな存在だった。だが、1980年代以後には姿を消していき、顧みられることは少なかった。2015年以後、テクニカル・エンジニアのケン・ハーシュが率いるORPHAN AUDIOがQUAD EIGHT〜ELECTRODYNE製品のリイシューを進めているが、その歴史についての情報は乏しい。オフィシャルな資料は無いので、当時のカタログや人々の断片的な証言が拾い集めていくしかない。
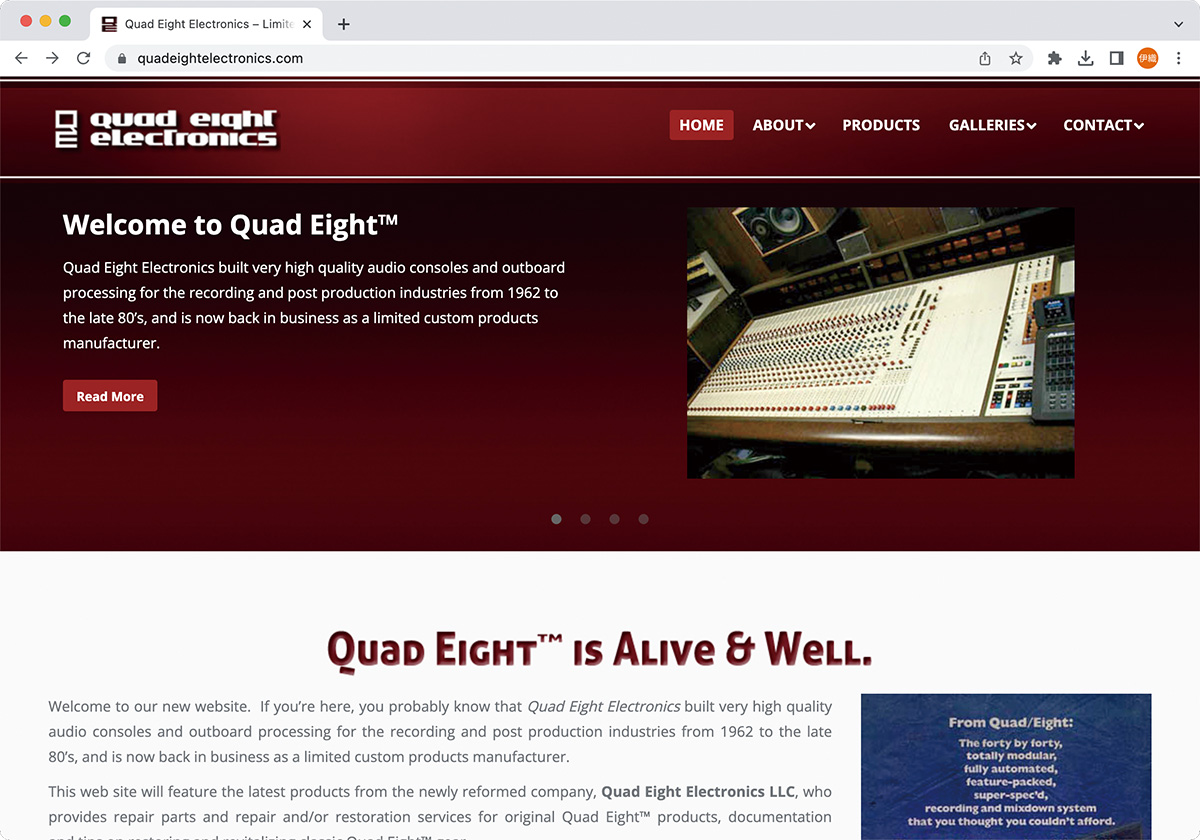
https://www.quadeightelectronics.com/
ELECTRODYNEのトランジスター回路の基礎を作ったのは同社のジョン・ホールというエンジニアだったという。そのホールが設計した回路を利用して、ミキシング・コンソールの製作を企画したのが、QUAD EIGHTのバド・ベネットだったようだ。ベネットはMGMなどの撮影スタジオで働いたキャリアを持ち、1960年代の初頭にQUAD EIGHTを設立。そのネーミングは8mmフィルム×4本を1本の35mmフィルムとして現像し、その後に4本に切り分ける技術から来ているという。映画産業に強い営業力を持っていたバド・ベネットが映画会社各社にミキシング・コンソールを売り込み、ELECTRODYNEにその製作を依頼するという形で、両社のビジネスが始まったようだ。
その後、ほぼ同一の構成を持つコンソールが、ELECTRODYNEあるいはSPHEREというブランドでも販売されるようになった。これらのコンソールはワーナー、ユニバーサル、20世紀フォックスなどのロサンゼルスの映画制作会社のスタジオに導入され、1960年代後半に急速にシェアを伸ばした。だが、フィルム・スタジオに納品されたQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEのコンソールについては、記録はあまり残っていない。
ロサンゼルスには映画会社系列のレコード・レーベルも多かった。だが、ワーナー系レーベルの作品でQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEのコンソールが使われていたかというと、そうとは限らないようだ。1960年代の後半から70年代の前半にかけて、ワーナーあるいはワーナー系列のリプリーズ・レーベルが生み出したサウンドに対して、日本では“バーバンク・サウンド”という言葉がよく使われる。ロサンゼルスの北にあるバーバンク市にはワーナーの映画スタジオがある。その歴史は1920年代に遡る。1927年に最初期のトーキー映画『ジャズ・シンガー』を成功させたワーナーは、バーバンクに巨大な撮影/録音施設を築き上げていった。このワーナーのバーバンク・スタジオがQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEの主要なクライアントだったのは間違いない。

だが、日本で“バーバンク・サウンド”と呼ばれるものがバーバンクで制作されていたかというと、そうではなかった。1958年にワーナーはバーバンクの施設の一角にレコード会社を設立する。だが、映画音楽やコメディ・レコードを手掛ける当初のワーナー・レコードの活動は小規模なものだった。
リプリーズ・レコードとテッド・テンプルマン率いるハーパース・ビザール
ワーナーは1960年にフランク・シナトラとの共同出資でリプリーズ・レコードを設立。1963年にシナトラから株を譲り受け、リプリーズを100%出資の会社としたころから、ワーナーのレコード業界での躍進が始まる。リプリーズの社長となったモ・オースティンの主導により、フォークやロックの分野でもワーナーは積極的にアーティストを発掘するようになった。1966年にはレニー・ワロンカーが入社。ワロンカーはリバティ・レコードの設立者であるサイモン・ワロンカーの息子で、スナッフ・ギャレットやトミー・リピューマの下でアシスタントを務めた経験も持っていた。ワロンカーがA&Rとなり、彼の周辺の若い才能たちと作り始めたのが、日本で言うところの“バーバンク・サウンド”とされるものだ。

その象徴的存在はハーパース・ビザールというグループだった。ハーパース・ビザールでは後にワーナーのハウス・プロデューサーとなり、ドゥービー・ブラザーズやヴァン・ヘイレンの大ヒットを生み出すテッド・テンプルマンがシンガーを務めていた。ハーパース・ビザールは1967年にデビュー・アルバム『フィーリン・グルーヴィー』を発表するが、その冒頭はヴァン・ダイク・パークスが作曲した「カム・トゥ・ザ・サンシャイン」だった。アルバムにはワロンカーの幼なじみだったランディ・ニューマンの曲も3曲収められている。ハーパース・ビザールの1969年のアルバム『4(ソフト・サウンディン・ミュージック)』のセッションにはライ・クーダーも参加している。後にソロ・アーティストとしてワーナー/リプリーズからデビューし、長いキャリアを築き上げていく彼らが、ハーパース・ビザールの裏方だったのだ。
テッド・テンプルマン/グレッグ・レノフ
迫田はつみ訳
(2022年/シンコーミュージック)
ハーパース・ビザールを経てプロデューサーへ転身し、ドゥービー・ブラザーズやヴァン・ヘイレンを手掛けたテンプルマンの自伝の邦訳。原著は2020年刊行
Harpers Bizarre
(1967年/Warner Bros.)
アレンジャーとしてランディ・ニューマン、ロン・エリオット、レオン・ラッセル、ペリー・ポトキンJr.らが参加。アルバム・タイトルは収録したサイモン&ガーファンクルのカバー「59番街橋の歌(フィーリン・グルーヴィー)」より
Harpers Bizarre
(1969年/Warner Bros.)
映画『太ももに蝶』の主題歌「I Love You, Alice B. Toklas」のほか、ザ・ビートルズ「ブラックバード」、ネイティブ・アメリカン系ジャズ・サックス奏者ジム・ペッパーの「ウィッチ・タイ・ト」などを彼らなりの解釈で収録。日本盤の副題(「Soft Soundin' Music」)はA面1曲目に収録したオリジナル曲より
だが、ハーパース・ビザールのアルバムがバーバンクで制作されていたかというと、そうではないようだ。ワーナー・レコードはバーバンクの撮影施設内のレコーディング・スタジオを使うことは少なく、ロサンゼルス市内のスタジオを転々としていたという。スタジオのクレジットは無いが、レオン・ラッセル、ペリー・バトキンJr.、ジャック・ニッチェといった顔ぶれが編曲や演奏を手掛けているところからして、ハーパース・ビザールの録音はウェスタン・レコーダーズなどで行われていたものと思われる。エンジニアは1966年にワーナーに入社したリー・ハーシュバーグで、彼はウェスタン・レコーダーズの出身だ。
ワーナー/アミーゴ・スタジオでの名録音を残したコンソールは?
1971年になって、ワーナー・レコードはようやく自社スタジオを構える。だが、それはバーバンクではなく、ノース・ハリウッドのコンプストン・アベニューにあったスナッフ・ギャレット所有のアミーゴ・スタジオをワーナーが買収したものだ。ワーナーによる買収後も同スタジオは以前の名前で呼ばれることが多かったようで、混乱を招きがちだが、アーロ・ガスリーの1976年のアルバム『アミーゴ』のクレジットを見ると、ワーナー・レコーディング・スタジオとアミーゴ・スタジオが同じスタジオだったことが分かる。

https://twitter.com/GregRenoff/status/1507380771975319564
Arlo Guthrie
(1976年/Reprise)
1947年生まれ、1967年デビューのフォーク・シンガーによる1976年作品。ラス・カネケル(ds)、リー・カンケル(k)、リンダ・ロンシュタット(vo)らが参加。
スナッフ・ギャレットは同スタジオを1968年にサックス奏者のスティーヴ・ダグラスから買い取っている。スタジオを整備したのは、当時はロサンゼルスでスタジオ・テクニシャンとして働いていたJ・J・ケイルだった。カー・バッテリーで動いていた古いコンソールをケイルが直したという逸話からして、それはQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEではなさそうだ。
ノース・ハリウッドのワーナー・レコーディング・スタジオは1972年ごろから本格稼働する。ドゥービー・ブラザーズは1972年の『トゥールーズ・ストリート』以後の4枚のアルバムを同スタジオで、プロデューサーのテッド・テンプルマン、エンジニアのドン・ランディとともに制作している。リー・ハーシュバーグも数多くの名録音を残している。とりわけ、マリア・マルダーの1973年のデビュー・アルバム『オールド・タイム・レイディ』(原題:Maria Muldaur)やライ・クーダーの1974年の『パラダイス・アンド・ランチ』などは素晴らしいサウンドだ。
Doobee Brothers
(1972年/Warner Bros.)
マイケル・ホサック(ds)が参加し、ジョン・ハートマン(ds)とのツイン・ドラム体制を確立した2nd。この後、3人目のギタリストとしてジェフ・バクスターを迎え、ボーカルがマイケル・マクドナルドに代わるまでの作品をアミーゴで録音する
Maria Muldaur
(1973年/Repries)
ジャグ・バンドで1960年代から活躍してきたマリア・マルダーのソロ・デビュー作。「真夜中のオアシス」「スリー・ダラー・ビル」などヒット曲を収録。ライ・クーダー、デヴィッド・リンドレー、クラレンス・ホワイト、ドクター・ジョンらがバックアップ
ライ・クーダー
(1974年/Repries)
スライド・ギターの名手による4thアルバム。「ディティ・ワ・ディティ」ではジャズ・ピアニストのアール・ハインズと共演。
この時期にメインのAスタジオで使用されていたのは、残された写真からAPIのモジュールを使ったコンソールだと分かる。1979年のライ・クーダーのアルバム『バップ・ドロップ・デラックス』(原題:Bop Till You Drop)の同スタジオでのセッションの写真にはNEVEコンソールが写っているから、1970年代の後半にAPIからNEVEに替わったのだろう。ワーナー系のいわゆる“バーバンク・サウンド”はバーバンク市で制作されていて、そこではQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEのコンソールが使われていたに違いない、と考えていた時期が僕にもあったのだが、それは間違った認識だったようだ。
ボブ・ディラン&ザ・バンドとウッドストックのベアズヴィル・スタジオ
では、音楽界でQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEのコンソールが活躍した代表例はというと、そこではインディペンデントなレコーディング・スタジオが挙げられる。東海岸ではニューヨーク市郊外のウッドストックに建設されたベアズヴィル・スタジオだ。
ベアズヴィル・スタジオはボブ・ディランのマネージャーだったアルバート・グロスマンによって、1970年に建設された。ニューヨーク州アルスター郡のウッドストックはニューヨーク市内からバスで2時間ほどの山中にあるが、1964年にグロスマンが、1965年にはボブ・ディランが移住した。1966年の夏に交通事故を起こしたディランは、以後、ウッドストックで隠遁生活を送り、ザ・バンドのメンバーとともに後に『地下室(ザ・ベースメント・テープス)』として発表されることになる数多くのデモ・レコーディングを行った。録音に使われたのはザ・バンドのメンバーが共同生活するビッグ・ピンクと呼ばれる一軒家だった。

https://bearsvilletheater.com/bearsville-studios/

https://bearsvilletheater.com/music-legacy/albert-grossman/
ザ・バンドは1968年に『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』というデビュー・アルバムを発表する。このレコーディングは、実際にはニューヨークのA&Rスタジオとロサンゼルスのキャピトル・スタジオで行われたのだが、田舎の一軒家から生み出される音楽というイメージは大きく、多くのミュージシャンがウッドストックに移り住み、コミューンを生み出すに至った。そこでグロスマンはウッドストックに本格的なレコーディング・スタジオを建設しようと考えた。
東海岸では1970年にジミ・ヘンドリックスがニューヨークのグリニッチ・ヴィレッジにエレクトリック・レディ・スタジオを建設。同スタジオはヘンドリックスの死の3カ月前に正式オープンした。エレクトリック・レディ・スタジオを設計したのはジョー・ストーリクという建築家だった。機材面はエンジニアのエディ・クレイマーが選定。コンソールはヘンドリックスのアルバム『エレクトリック・レディランド』で使用されたニューヨークのレコード・プラントと同じDATAMIXのコンソールが採用された。だが、DATAMIXは財政難にあり、ほどなく解散した。
グロスマンはベアズヴィル・スタジオの設計を同じくジョー・ストーリクに依頼。ストリークは郊外型の新しいスタジオの建築を構想することになった。機材面はチーフ・エンジニアのテッド・ロステインに任された。ロステインはQUAD EIGHT〜ELECTRODYNEのMM310というマイクプリ/EQモジュールを使ったカスタム・コンソールを選択した。このMM310はフィルム・スタジオ用のコンソールに多く使われたモジュールのようで、当時のカタログには12色ものカラーリングが見られる。現代のスタジオでもカラフルなモジュールがラッキングされているのを見かける。

ベアズヴィルで若き才能たちが触れたQUAD EIGHT MM310のサウンド
スタジオ建設中の1970年に、グロスマンはベアズヴィル・レコードを設立した。これはアンペックス・レコードに原盤供給する契約レーベルで、その第1弾はアメリカン・ドリームというバンドだった。グロスマンはそのプロデュースとエンジニアリングをトッド・ラングレンに任せた。当時のトッドはソロ・ミュージシャンとしてデビューする前で、エンジニアの道を歩もうとしていたのだ。

Photo:Mitchell Weinstock
CC BY 2.0
アメリカン・ドリームはニューヨークのレコード・プラントで1枚のアルバムを制作した後に解散。シンガー/ギタリストのニック・ジェイムソンはエンジニアに転じた。1971年にオープンするベアズヴィル・スタジオには、トッド・ラングレンとニック・ジェイムソンもエンジニアとして参加することになった。スタジオの完成と前後して、ベアズヴィル・レコードはアンペックスとの契約を解消し、ワーナー系のレーベルとなった。

ザ・バンドのアルバムでは1971年の4作目『カフーツ』がベアズヴィル・スタジオで制作されている。このアルバムのインナー・スリーブには建設中のベアズヴィル・スタジオの内部を見ることができる。メンバーがフォト・セッションしている大きな体育館のようなスペースはスタジオAで、ここは当初はリハーサル・ルームに使われた。MM310モジュールを使ったカスタム・コンソールが設置されたのはスタジオBで、シリアスなレコーディングはこちらでスタートした。

https://web.archive.org/web/19991117084749/http://www.bearsvillestudios.com/studa.html
The Band
(1971年/Capitol)
アラン・トゥーサンが「カーニバル」のホーン・アレンジに、ヴァン・モリソンが「4% パント・マイム」のボーカルに参加。2021年にはロビー・ロバートソンとボブ・クリアマウンテンによる新ミックスも収録した50周年記念エディションが発売
トッド・ラングレンの『“ラント”ザ・バラッド・オブ・トッド・ラングレン』(1971年)、ボビー・チャールズの『ボビー・チャールズ』(1972年)、ボニー・レイットの『ギヴ・イット・アップ』(1972年)なども開設当初のベアズヴィル・スタジオで生み出された名盤だ。ウッドストック在住のミュージシャンが数多く参加した『ギヴ・イット・アップ』のインナー・スリーブからは、当時の同スタジオの雰囲気がうかがい知れる。狭いコントロール・ルームでミュージシャンたちが身を寄せ合って、モニターを聴いている写真もあり、QUAD EIGHT MM310モジュールを使ったコンソールも確認できる。レコーダーはAMPEX M1000の16trで、アウトボードにはPULTECのEQ、TELETRONIX LA-2A、LA-3A、UREI 1176なども見える。『ボビー・チャールズ』や『ギヴ・イット・アップ』に聴けるバンド・サウンドは、QUAD EIGHT 〜ELECTRODYNEの音質を知る上でも好サンプルになるだろう。NEVEのような重さはなく、立ち上がりが良くて、明るさもあるが、決して線は細くなく、骨太な感触もある。筆者は1990年代に一度だけ、都内のスタジオでQUAD EIGHTのコンソールを使用したことがあるが、その時の印象とも共通する。

https://wsdg.com/projects-items/bearsville-theater/
Bonnie Raitt
(1972年/Warner Bros.)
2ndアルバム。エイモス・ギャレット(tb)、エリック・カズ(vib、p、他)、ポール・バターフィールド(harm)など多くのミュージシャンが脇を固め、フォーク、ブルース、 R&B、ブラス・バンドなどさまざまな音楽性を取り込んだ。


高橋健太郎
音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。Twitterアカウントは@kentarotakahash
Photo:Takashi Yashima




