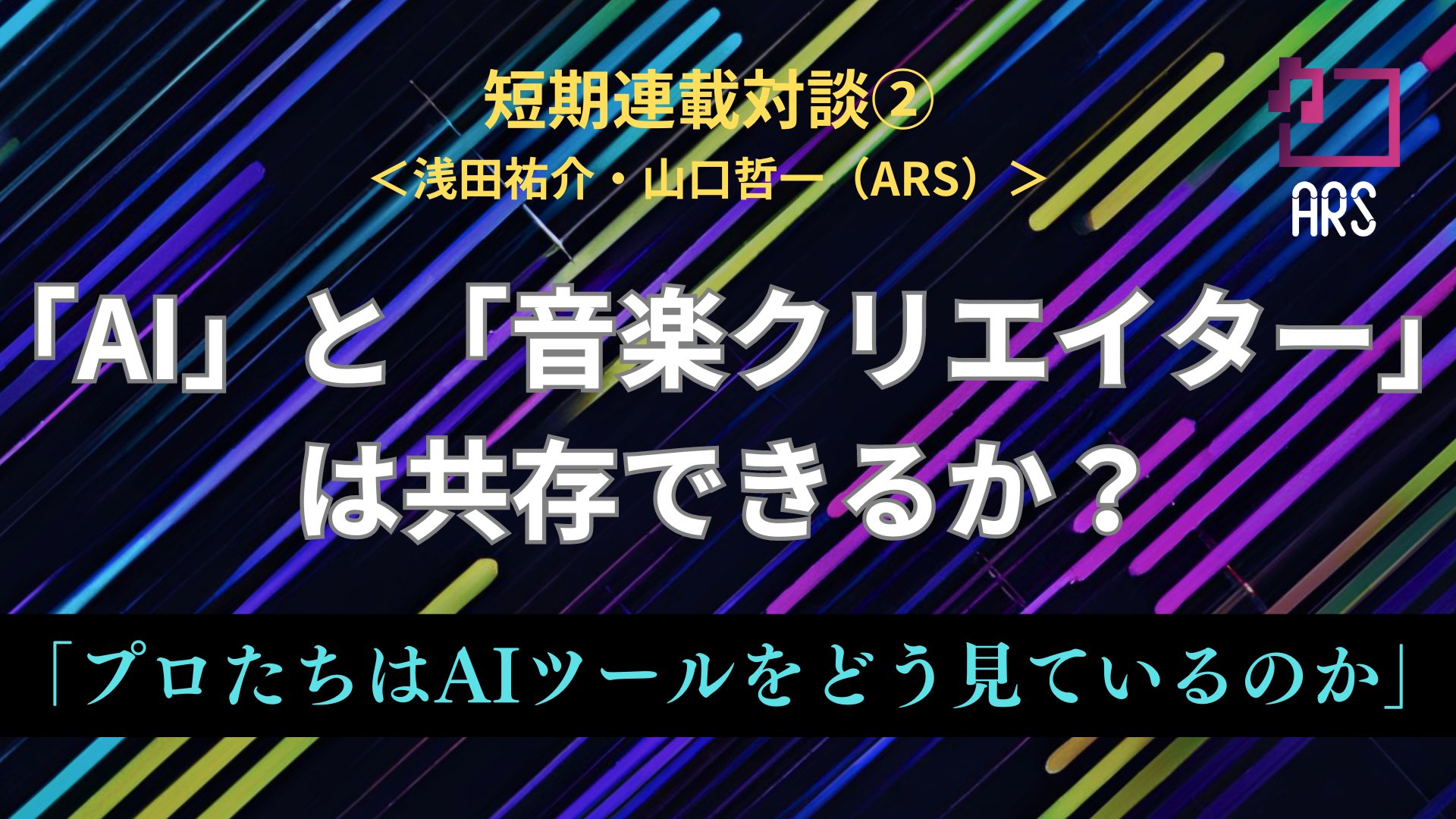
サンレコWEBでは異例なテーマの連載として始まった本連載。前回は、音楽創作/制作においてAIが果たす役割の“本質”を見極めるべく、浅田祐介・山口哲一の両氏が独自のアイディアを披露してくれました。二人が共同代表として始めた“ARS”の活動も紹介していますので、よろしければチェックいただけたらと思います。
さて、第2回は4月6日・7日に行われたイベント『ARS presents VX-β 作家ソン』を浅田・山口の対談から振り返っていきます。イベントに参加されたプロ・クリエイターたちの肉声も交えつつ、AIと作曲家の関係について一緒に考えていきましょう。

浅田祐介
【Profile】音楽プロデューサー、コンポーザー、ミュージシャン。1991年にCharaのサウンド・プロデューサーとしてキャリアをスタートし、その後CHEMISTRY、Crystal Kay、キマグレンなどトップ・アーティストの作品を数多く手掛け、1995年にはシンガーとしてもデビュー。エニシング・ゴーズ代表。JSPA(日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ)理事
山口哲一
【Profile】音楽プロデューサー、エンターテックエバンジェリスト。起業家育成と新規事業創出を行うスタートアップスタジオ、StudioENTRE代表取締役。知的財産戦略本部コンテンツWG委員、iU超客員教授。プロ作曲家育成「山口ゼミ」主宰。Web3✕音楽の中心地「MID3M+」ファウンダー。『コーライティングの教科書』『音楽業界の動向とカラクリがわかる本』他著書多数。『AI時代の職業作曲家スタイル~逆張りのサバイバル戦略』6月12日発売予定。https://note.com/yamabug
AIシンガーを用いてプロたちがハイレベルな共作を行った『作家ソン』

山口 少し時間が経っちゃいましたけれど、『作家ソン』はめちゃめちゃ楽しかったですね。司会をやりながら興奮したのは久しぶりでした。
浅田 10年くらい前に山口さんとやっていたハッカソンと作家で“作家×ハッカソン=作家ソン”という、語感の良さで僕らは盛り上がりましたけど、参加者の方々も本当に楽しんでもらえて、やってよかったなぁと思いました。
山口 4月6日・7日の2日間で作家がチームを組んで新たな創作を行いました。これは3月7日から、VX-βで僕らが独自に作ったAIシンガー“L”をプロの作家約40人に配って、自由に創作をしてもらったプロジェクトの取りまとめの場も兼ねています。楽曲はYouTubeにアップしているので、そちらもぜひご覧いただきたいです。
その『作家ソン』の内容を振り返っていきましょう。複数の作家同士でチームを組み、計5組に分かれYAMAMAHのVX-β(VOCALOID β STUDIO)を使って2日間で作品を仕上げてもらう、という企画でした。どうでしたか?
浅田 本来、VX-βでは実装されてないラップを力技でやっていたり、ボイス・チョッピングをしたり、何というかプロの情熱の極み。皆さんから何か驚かせてやろう、一泡吹かせてやろう、という思いが伝わってきました。
山口 そんな感じでめちゃめちゃ盛り上がった『作家ソン』ですが、フルサイズでYouTubeにアップしていますので、2時間40分と長尺ですが、時間があるときに早送りなどしながら見てみてください。最後にはVX-βを活用したライブもあって、音楽家にとって刺激になるシーンがたくさんあると思います。
浅田 なんだかんだライブでは僕も歌いましたし(汗)、ぜひ見ていただきたいですね。
山口 VX-βの技術を駆使したU-SKEの弾き語り、久々に歌声を堪能しました。

AIならではの動画やそれ以上の創作が出てきたら面白い
山口 今回は、『作家ソン』に参加したプロ作曲家たちの感想を紹介しながら、AI生成と音楽の関係について考えてみようと思います。ARSが企画した『作家ソン』については、皆さん「とても刺激になり、楽しかったです」というようなポジティブな感想を多くいただきました。「普段触れ合いのない一流の外部作曲家さんたちと交流ができ、とても楽しかったです。 また、AIボーカルによる実演など、音楽テクノロジーの最先端が見られて有意義な会だったと思います」というコメントで総括できる気がします。またやりたいですね。
浅田 はい、自分がワクワクしながら、携わっていただいたスタッフの皆さんや参加したクリエイター、視聴していただいた方々に喜んでもらえるというのはエンターテインメントの基本だなぁ、とあらためて実感しました。
山口 VX-βに関する忖度のない感想や、改善点への提案をYAMAHAの開発チームに共有できたのもよかったなと思います。音楽家と開発者が近い距離でコミュニケーションを取る機会って重要ですよね。打ち上げでもめちゃめちゃ盛り上がってたよね?
浅田 盛り上がりました! 僕個人としてはボカロは傍観者の立場で、面白いなぁと思っていました。カルチャーが生まれている現場をリアルタイムで見ていながら、当事者になれないもどかしさもあったりした中、あらためてYAMAHAの方々とつながれたのは幸運でした。そもそもAIシンガーやボカロのような技術は海外にもありましたが、それを利用したコンテンツがこんなにある国は日本だけで、これをうまく利用できたら面白いことが起きるのでは!と思いました。
山口 僕たちがAIシンガーと呼ぶことにしたムーブメントに対しては、こんな感想があって、なるほどなと思ったので紹介します。「Auto-Tuneで音程の悪い歌がすべて過去のものになったように、そこそこのクオリティで必ず歌ってくれる生成AIの登場で、下手な歌は過去のものになりそうです。もしくは逆に人間味があるものが評価されるかも? 時代の流れを読む必要がありそうです」。

浅田 メタ認知能力が問われると思います。常々山口さんがおっしゃている、「クリエイティブだと思っていたものが、実は単なるスキルだった」という時代がすぐそこに来ています。海外でのチャートやSpotifyのEarly Noiseの中では微分音やポリリズムを使ったポップス、AIでまだ学習されていない手法を使った音楽が作られてきています。さらにメインストリームにはなり得ないですが、AIで作った曲、AIで作ったジャケット・アート、AIで作られたメタヒューマンなど、すべてAIで作られたアーティストの試みもありました。
山口 テクノロジーの進化が新しいアートフォームを生んでいるんですね。アンケートの中で、歌声生成だけではなく、AI全般と音楽の関係性については、「避けて通れないので、うまく取り入れたい」「今後なくてはならないツールのうちの一つになっていくと思っています」というコメントが一般的な受け止め方なのかなと思いました。
一方で、「うまく取り入れて共存したい気持ちと、アナログな自分の創作にこだわりたい気持ちの両方あります」という意見や、逆に「AIは自分の分身的に感じます。大いにプラス嗜好でポジティブに捉えています」という意見もあって興味深かったです。
浅田 はい、SoraやVeoのように動画生成のサービスが始まると、今までミュージシャンが言葉では説明できるけど、実際に映像化するためのスキルがないので諦めていたMVなどの映像表現が、ハイクオリティかつローコストで作れるようになります。もちろんミュージシャンの本業は音楽ですが、シンガー・ソングライターがそれまで分業だった作詞/作曲/歌唱を一つにしたように、AIをツールとして使って動画やそれ以上の表現をするようなアーティストが出てきたら面白いなぁと思います。
AIを使う/使わないは自由だが、時代に対する感度は鋭くありたい
山口 僕が注目したのは次の回答です。「今回、楽曲をYouTubeに上げるために初めてイラストをAIで作成しましたが、便利過ぎて感動しました。 メロディをAIで作ることに興味は持てませんが、 仮歌発注データを作ってくれるとか、エディットをいい感じにしてくれるとか、持っている音源からマッチする音色を提案してくれるとか、楽譜のレイアウトやパート譜作りを代わってくれるとか……進化したらもっと音楽にかけられる時間が増えて楽しそうと思っています。もしかしたら職を失うのかもしれませんが(笑)、自分が曲を作ることに変わりないので、そうなっても受け止めます」。いずれにしても今の段階からAIと音楽について意識的であることが大切ですよね?
浅田 そう思います。使う/使わないは各々のクリエイターの選択ですが、新しい流れが出てきたなぁ、ぐらいは知っていることが大事だと思います。そもそも感度が鈍いクリエイターって需要は低いですし。
山口 今回紹介した企画の内容も踏まえて、6/12に出版する『AI時代の職業作曲家スタイル 逆張りのサバイバル戦略』(小社刊)の一番長い章、AIに関する部分を浅田さんと二人で書きました。ぜひ皆さんに読んでいただきたいです。出版直前の6/8に内容チラ見せを含んだ、オンライン・トークイベントを二人でやりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。
浅田 新しい楽器が出たな、ぐらいの気持ちで読んでいただけたらと思っています。またトーク・イベントでは本に書けなかった話などもしたいので、ぜひチェックしてみてください。
山口 次回は、この書籍を書くために体験したさまざまなAIツールに関して、サンレコらしく具体的に紹介しますのでお楽しみに。
関連リンク
【2024/6/8(土)13:00〜オンライン開催】書籍『AI時代の職業作曲家スタイル 逆張りのサバイバル戦略』出版直前イベント~「AIとポジティブに向き合う方法」 出演:山口哲一、浅田祐介



